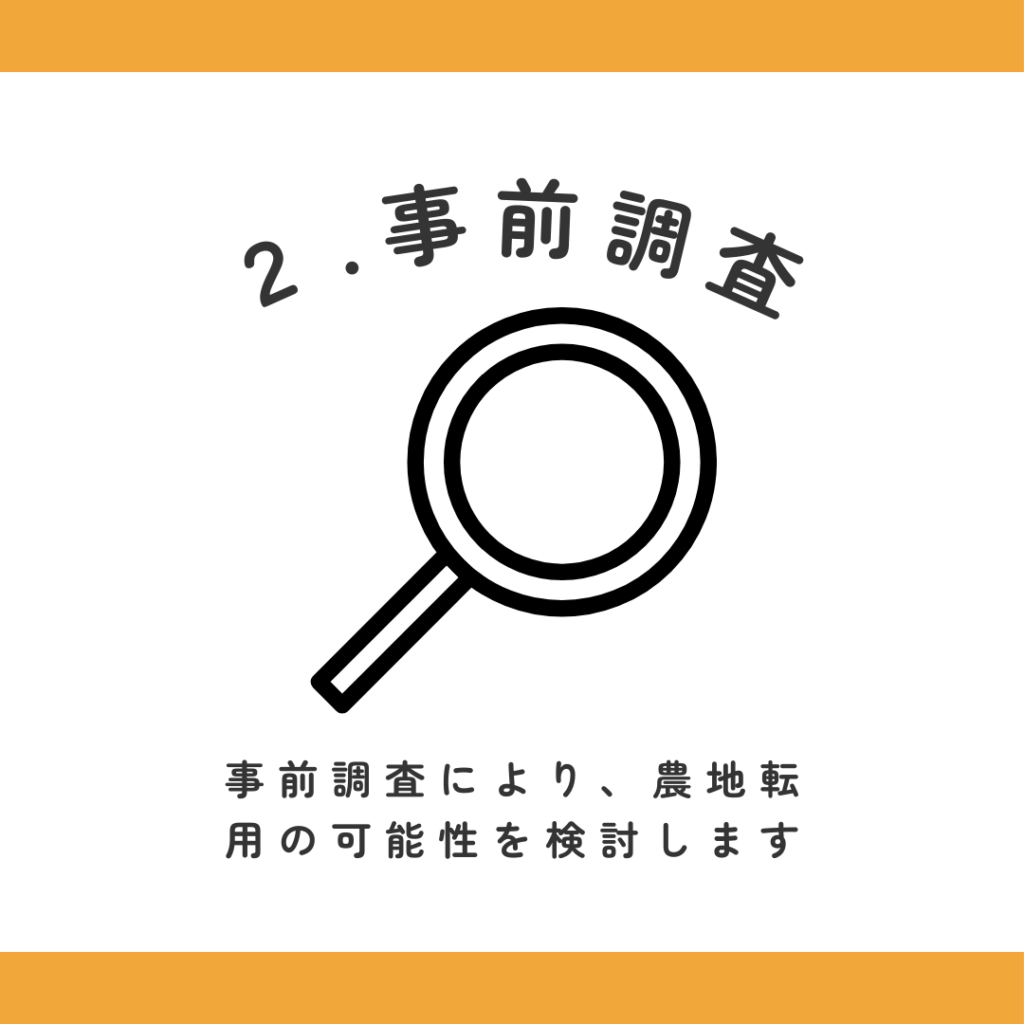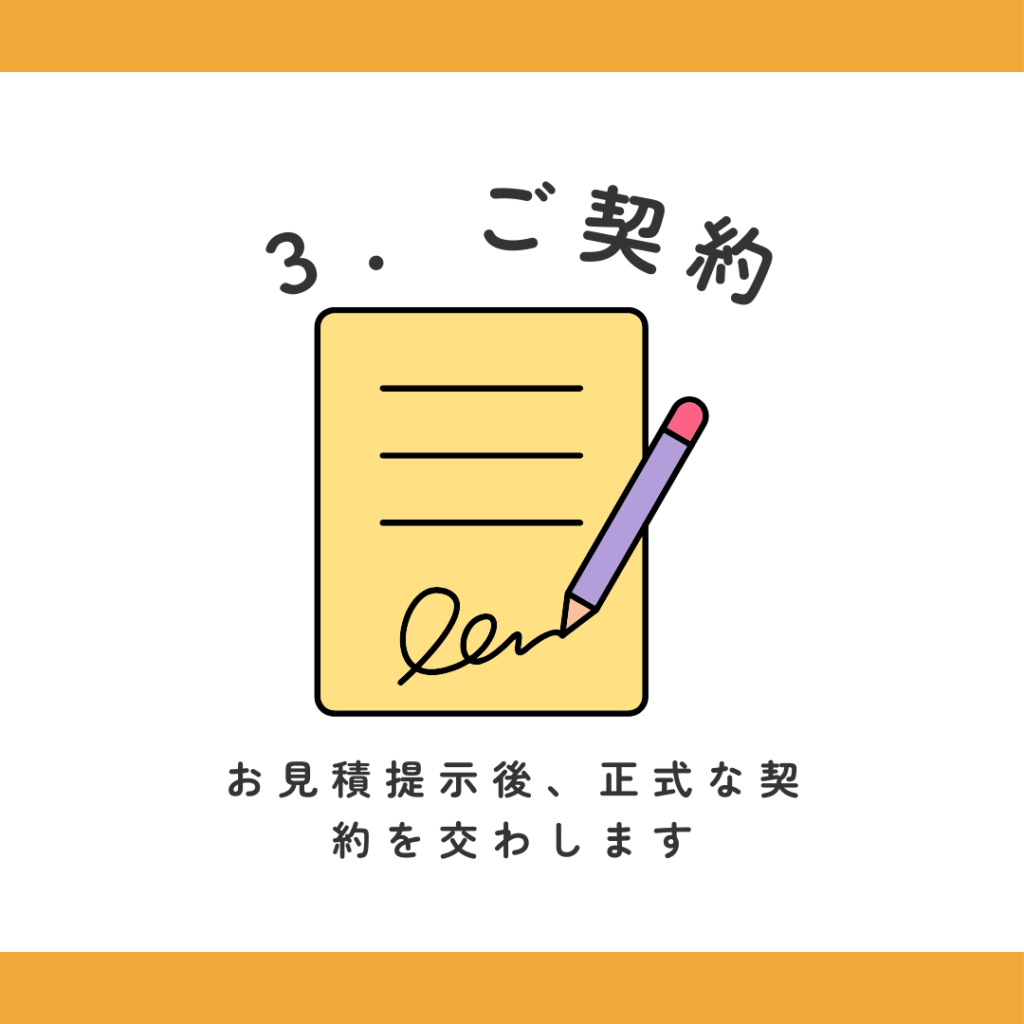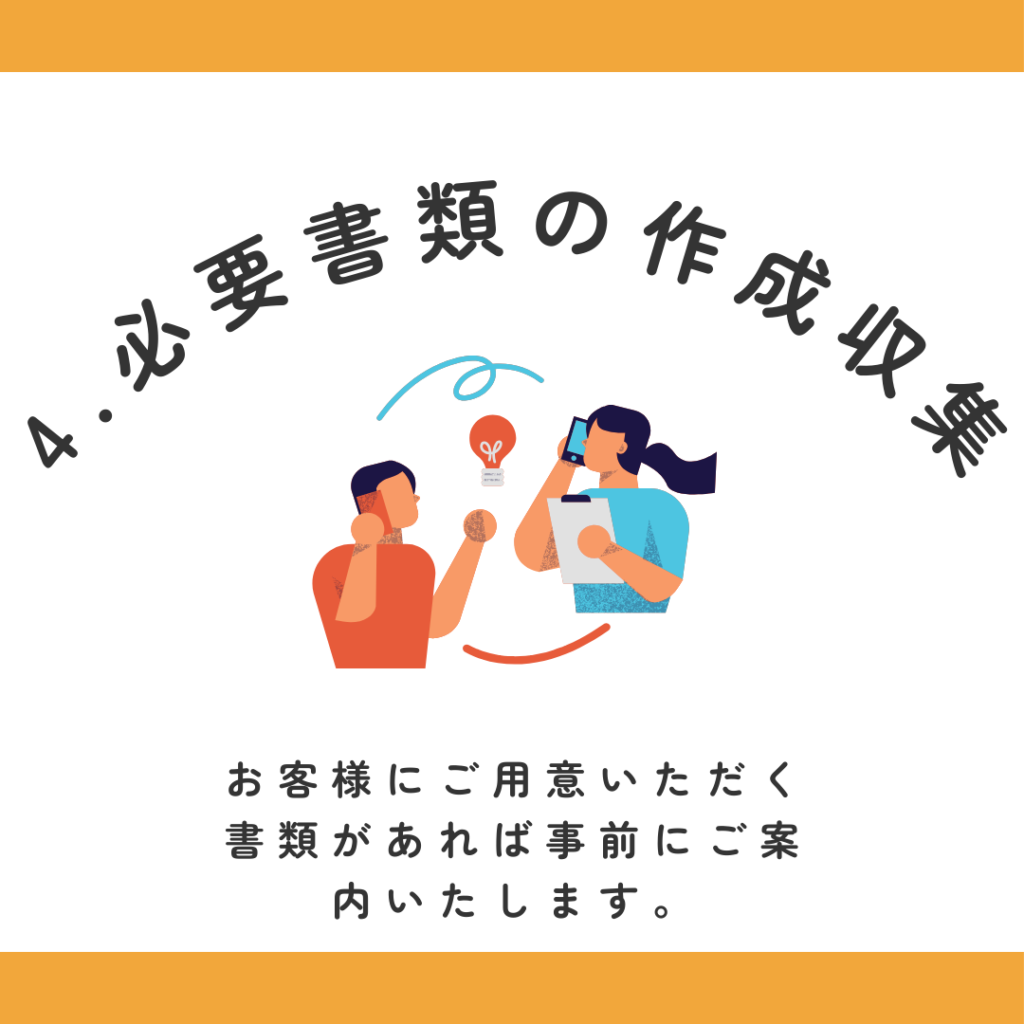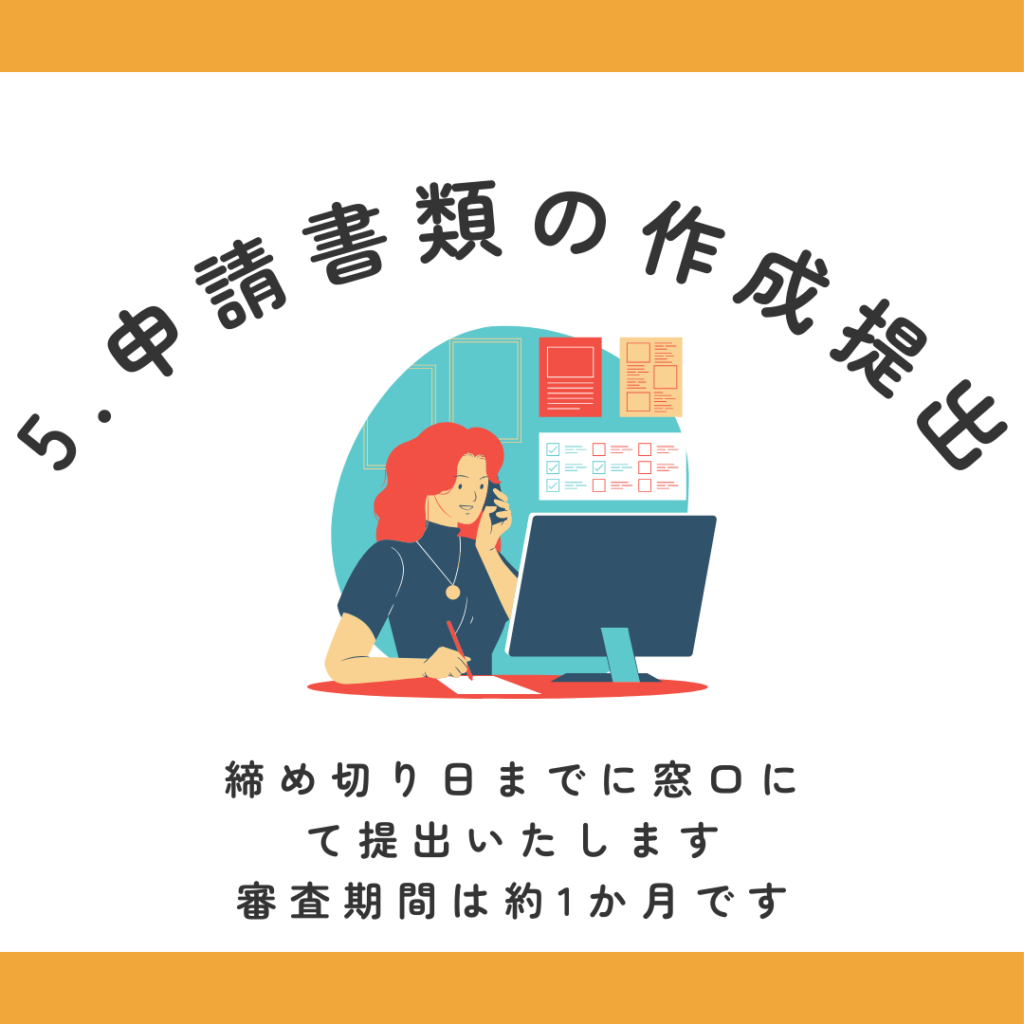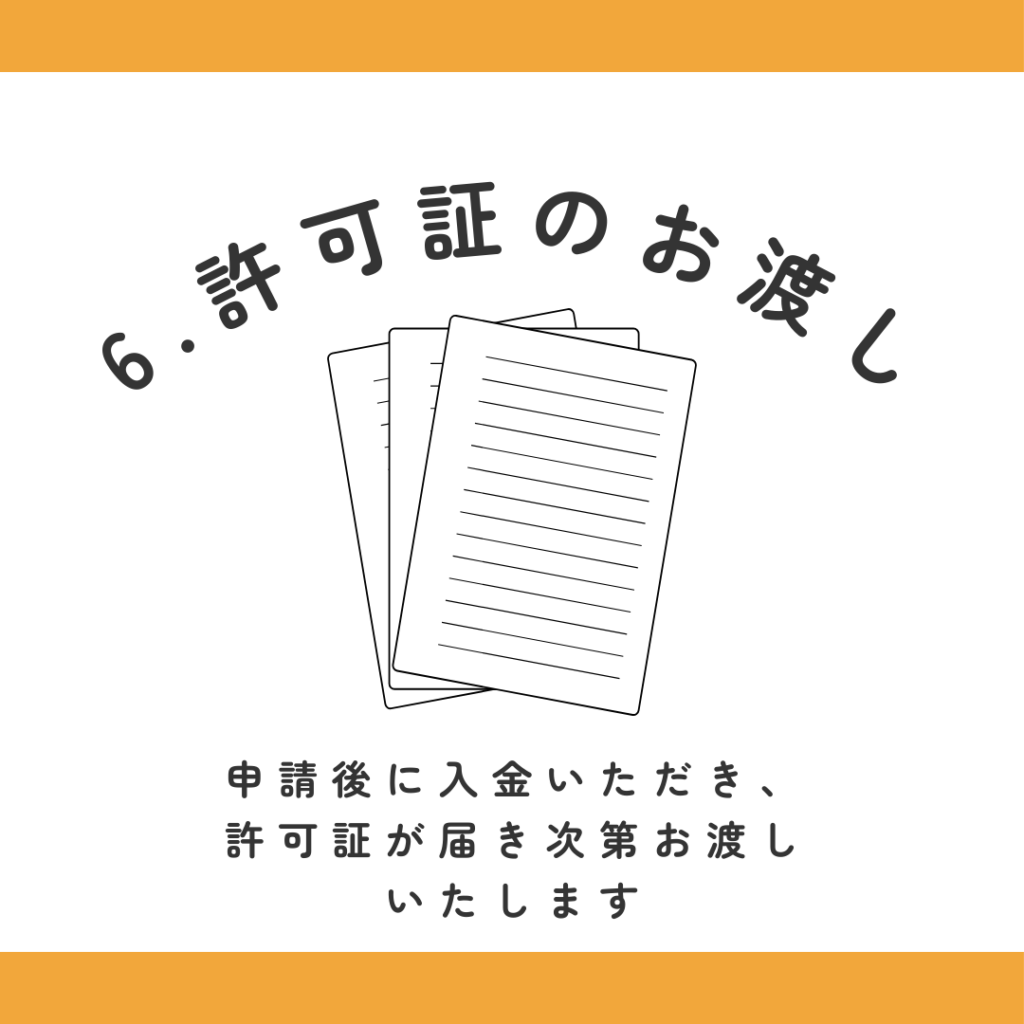こんにちは。群馬・埼玉を中心に農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。
今回は、農地を資材置き場にする方法について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。
詳しく見ていきましょう!!
はじめに
農地を「資材置場」にしたい、という相談はとても多いテーマです。建築現場の資材や機材を置くために一時的に使いたい方もいれば、会社の恒常的なヤードとして整備したい方もいます。ただし、農地は法律上「農業に使う土地」として守られているため、そのままでは資材置場に利用できません。ここで関わってくるのが 農地転用許可 と 開発許可 です。
1.農地転用許可とは?
まず、農地を農地以外に使うためには「農地法」に基づく 農地転用許可 が必要です。
資材置場は明らかに農業目的ではないため、農地をその用途に変えるなら必ず転用の手続きが求められます。
- 自己所有の農地を自分で使う場合 → 農地法4条許可
- 他人に売る・貸す場合 → 農地法5条許可
自治体によっては「市だけで判断できる場合」と「県と協議が必要な場合」があり、規模や場所(市街化区域か、市街化調整区域か)によっても難易度が変わります。
2.開発許可とは?
農地を資材置場にする場合、単に転用するだけでなく「整地」「舗装」「フェンス設置」などを行うケースが多いです。
その工事が「都市計画法」でいう 開発行為 に当たる場合、農地転用許可に加えて 開発許可 が必要になります。
下記、開発行為になるケース
- 造成(盛土・切土など)
- コンクリートやアスファルトで全面舗装
- フェンスや建築物を伴う資材置場
一方で、砂利を敷いただけで出入りも限定的な簡易利用なら「開発行為に当たらない」と判断されることもあります。
ただし、自治体ごとに基準が異なるため、必ず事前相談が必要です。
3.転用許可と開発許可の関係
ここが混乱しやすいポイントです。
- 農地転用許可は「農地を農地以外にして良いか」を問う手続き
- 開発許可は「その土地利用のために行う工事をして良いか」を問う手続き
つまり、資材置場にする場合は 両方の許可が必要になることが多い のです。
農地転用許可だけを取っても、舗装工事やフェンス設置をするなら開発許可なしでは進められません。逆に、開発許可が下りても農地転用許可を忘れると違法利用になってしまいます。
4.注意点
- 事前調査が大切
どこまで工事するか、排水はどうするか、周辺の土地利用に影響がないかを確認します。 - 自治体によって扱いが違う
ある市では「砂利敷きなら転用許可だけでOK」と言われても、隣の市では「開発許可が必須」とされることもあります。 - 規模が大きいほど厳しくなる
500㎡や1,000㎡を超えると開発許可の対象になる可能性がぐっと高まります。
まとめ
農地を資材置場にするには、基本的に 農地転用許可は必須。さらに整備内容によっては 開発許可も必要になります。
どちらの許可が要るかは土地の場所・面積・工事内容で変わるため、まずは役所に事前相談するのが一番の近道です。
資材置場は「とりあえず空いている農地を使いたい」と考えがちですが、法律のハードルは意外と高め。しっかり準備すれば、スムーズに許可が進み、安心して使える資材置場を確保できます。
農地の手続きには専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。
よくある質問(Q&A)
農地を資材置場にするのに、必ず許可は必要ですか?
はい。農地は原則として農業に使う土地なので、そのまま資材置場にはできません。必ず農地転用許可が必要です。さらに舗装工事やフェンス設置などをする場合は、開発許可も求められるケースがあります。
砂利を敷いただけなら開発許可はいりませんか?
自治体によって扱いが異なります。ある市では「転用許可のみでOK」と判断されても、別の市では「開発許可も必要」と言われることがあります。必ず事前に市役所や県の担当部署に確認しましょう。
農地転用許可と開発許可、どちらを先に取ればいいですか?
通常は農地転用許可が先ですが、同時並行で進める場合もあります。自治体ごとに手続きの順序が違うことがあるので、事前相談で確認しておくのが安心です。
小規模(100㎡程度)なら許可はいりませんか?
面積が小さくても農地である限り転用許可は必要です。規模が大きいと開発許可の対象になりやすいですが、小さいからといって無許可で使えるわけではありません。
農地の転用でお困りですか?
農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
kamemizu-law@outlook.jp
業務の流れ
※対面をご希望の方は、こちらからお伺いいたします。